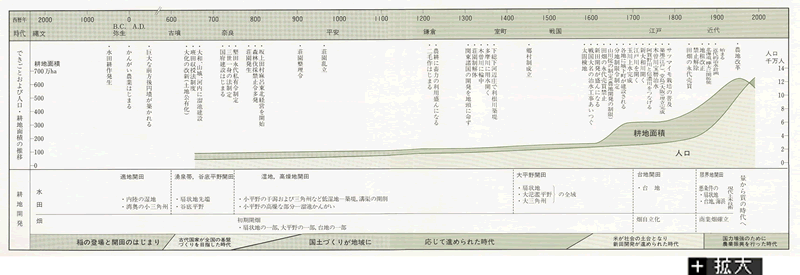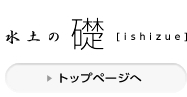人口の成長
第1の波: 狩猟・採集経済の極限
全国の縄文遺跡は、大半が東日本に集中しており、縄文期の人口も、このように分布していたと推定される。穏やかに増加する人口は縄文中期(紀元前2~3,000年ごろ)には全国で25万人余りに達した。
人口密度は、関東地方で300人/100km2、その他の東日本でも100人/100km2程度で、狩猟・採集経済社会としては発展の極限に達していた。これに対し西日本では、10~20人/100km2ほどであった。縄文中期以降、全体の人口は減少に転じ、また変動が急激になり、地域による差も出てくる。東日本で人ロが減少したのに対し、西日本では安定して推移し弥生期に顕著な増加をみせる。これは、東日本の人口は狩猟・採集経済の許容限度一杯に達しており、気候の悪化が食物の生産力の低下をまねいたからであろう。
第2の波: 稲作の登場
新しい文化は、紀元前3世紀ごろから九州北部におこり、各地に広がるとともに大きな社会的転換をひき起こし、人口は急速に増加しはじめた。稲作農耕が日本列島の主産業として定着し、人口支持力を大幅に増大させることとなったのであるが、水田耕作には大量の労働力を必要とし、この面からも人口増加が促され、開発が進んだ。こうした人口増と開発の相互作用がうまく働いて、8世紀には500~600万人に達した。
しかし、8世紀を過ぎて人口増は停滞した。この原因としては、当時の開発技術の限界もあるが、大きな要因は12世紀から14世紀にかけての気候の変化であり、『方丈記』などに描かれるように度重なる早魃で飢饉が続発した。また、荘園の収益権が複雑化するばかりで、領主・領民ともに開発を促す要因とはならなかった。
第3の波: 市場経済のはじまり
人口成長の第3の波は14、15世紀にはじまり、18世紀まで続く。これは市場経済への転換が起きたことによる。荘園体制下においては、貢納と自給に限られていたがそれでも14世紀ごろからは市場ができ、貨幣による交換が、特産物の売買などとともにはじまるようになった。このため、商品生産を目的に、農民たちは意欲をもって生産を進めた。隷属農民の労働力に依存する名主経営が解体して、家族労働力を主体とする小農経営が成立するのも、こうした生産力の高まりによる。戦国大名の領国経営や幕藩体制下における新田開発をはじめ、城下町の建設、河川工事、街道整備などがそれを助けた。
それとともに日常生活レベルでは、日常的な生活水準の上昇により死亡率は低下し、出生率は高まった。1日3食の定着など食生活の充実、木綿の普及による衣類の改善、畳の普及にみられる住生活の向上と、わが国の伝統的な生活様式が定着するのと軌を一にして、人口は増加した。こうして17世紀初めには1,200~1,300万人、18世紀初めには3,000万人に達した。
しかし、18世紀半ばからは人口はほほ安定し、江戸期末までは、3,000万人余りで推移した。このころ気候が寒冷化し、夏季の気温低下が凶作を生じさせ、飢餓とさまざまな病気が蔓延した。享保・天明・天保の飢饉は有名である。堕胎・間引といった産児制限も行われた。しかしながら、この人口停滞は、近代へ向かっての蓄積を可能にしたともいえる。
第4の波: 近代産業革命の成立
この時期までの基盤のうえに西洋技術が導入され、さらに、その後の技術革新や経済成長もあって、明治維新以降から人口は再び急増に転じ、明治元(1868)年に3,300万人であった人口は、100年間に4倍の増加を示し、昭和63(1988)年現在1億2,200万人となっている。このような人口の急激な増加は、江戸後期における農村工業の勃興による生産力の増大を契機としてはじまり、明治以降の産業革命の進展、医学の発展や衛生知識の普及、食糧供給力の向上、などによってもたらされたものである。
このように、わが国の人口は、経済社会制度の整備、農業の生産性向上のための土地や技術などの発達と成熟に対応して、それぞれ増加期と安定期を繰り返しながら増加してきた。
こうした人口増加は、耕地面積の増加と平行した線を描いており、農業社会であった日本の社会では、生存は農業生産いかんによっていた。環境によって左右される狩猟・採集経済社会から離脱して、弥生期の農業革命以降、人間が、与えられた環境のもとで生存のための食糧を自ら生産し、さらには環境を改変して生活を営んできた成果が、この2本の成長曲線になって現れている。