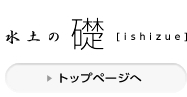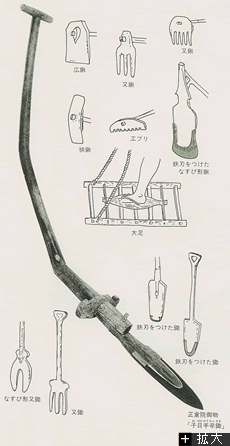古代のむら
農民層の階層分化
古墳期の集落は、その景観において、弥生期とは異なっている。8世紀の古墳期の遺跡は、建物の規模などにちがいはあるものの、主屋と1~2戸の付属屋、倉、井戸および作業場的な空間をもつ点で共通している。文献から知りうる家族構成などからみて、このような屋敷構成から、弥生期の小集落に認められた世帯共同体的小集団と似た性格の家族集団が想定される。しかしながら、弥生後期以降になると、中心的な大集落を核として分岐小集落が結びつく関係には、大きな変化が起こった。農民層の階層分化である。
階層分化の結果、むらの中でも上層に位置する人々が生まれた。また、明確な屋敷地をもてず、竪穴住居群の小集落をつくるもの、さらにその下層に、首長層や上層農民に隷属して、その屋敷地の内外に住まわされるものも生じてきた。さらに、古墳後期には、農業経営においてさまざまに規模の異なる経営が生まれた。小規模ながら自らの個別経営を維持できた人々を中間層とし、大規模経営の中に取り込まれた隷属民の分化が生じていたと思われる。
こうした階層分化に伴い、環濠で囲まれた大集落が解体した。それまで大規模な環濠集落に共同体成員とともに居住した首長層が、防御施設をもつ自らの屋敷地を別に設け、居住地においても成員から隔絶した。前方後円墳の成立に先立って首長層が共同墓地から飛び出し、一定規模の独立墳丘をもつ墳墓を築きはじめるのは弥生後期の新しい段階であるが、集落においてもこれと対応する変化が進行した。首長層たちは、濠や土塁や柵で囲った屋敷に住むようになり、やがてそれは小首長や有力農民にも普及していった。
独立して大規模な濠をめぐらした豪族の屋敷地は、一辺数十メートルの方形に整えられ、濠の排土で盛土し、縁辺部を河原石の石垣を築いて固めている。銅鐸に表現された建物の様相や家形埴輪などから、近畿地方を中心に西日本の各地で、5世紀以降に堀立柱の建物が出現し増加していく傾向が確実に認められる。豪族の居館も、そうした建物ではなかったか、と思われる。

家形埴輪
中央に竪穴式切妻造りの主屋があり、両妻に小型の切妻造り、両平には小型の入母屋造りの家を配した豪華な埴輪で、「子持ちの家」とも呼ばれ、隷属民を従えた有力な地方豪族の邸宅らしい姿を呈している。
(宮崎県西都原古墳出土.東京国立博物館蔵)
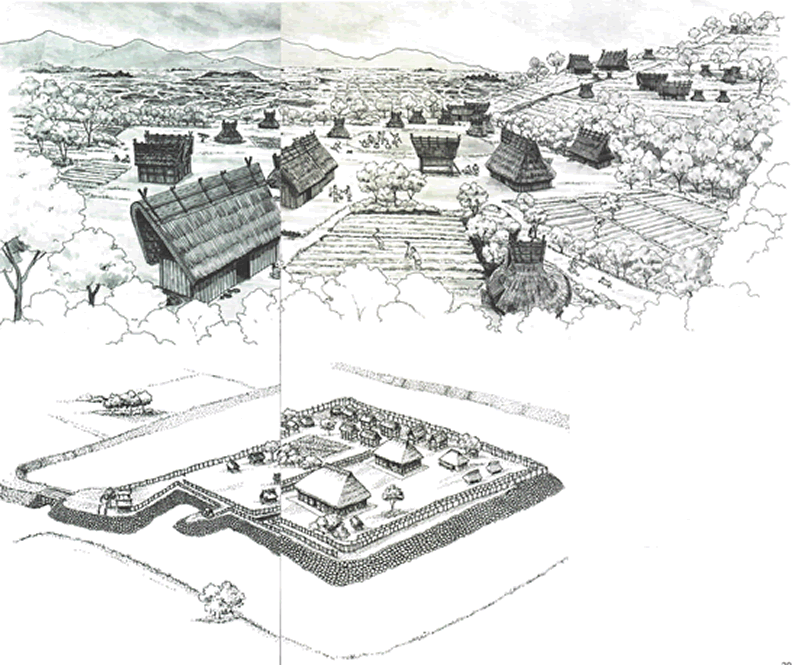
古代の豪族屋敷
群馬県群馬町で発掘された三ッ寺遺跡は一辺約86mの方形の区画を幅30mにおよぶ濠で囲み、濠の壁には古墳のように一面石張が施してあった。区画には三重の柵に囲まれた大小の建物が並ぶ。
鉄器の出現
弥生期の農具は、木製具が主役で、おもに強靱なカシ類を用いていた。鉄器は、「道具をつくる道具」であった。開墾用にも使用されたと思われる耕耘用具は、狭鍬・広鍬・又鍬などの鍬類と各種の鋤類がある。木製耕耘用具は、鉄製農具の普及によって、弥生期前半をピークとして以後は種類が減り、拵えの粗雑なものが現れる。広鍬が軽量の鍬へと変化し、狭鍬が粘質土の耕作に効力を発揮するとされ広く九州北部から関東におよぶ。
古墳期には、なすび形の鍬と鋤が耕具の中心となった。古墳期前半には、弥生中期にすでに出現していた長方形の鉄板の両端を折り曲げた鍬・鋤先が広まる。これらは大型の古墳に木工用の鉄器などとともに副葬されている。後半期になると刃部の両端が湾曲して全体がアルファベットのU字に似ているU字形の鍬・鋤先が登場し、普及する。これらは5世紀ごろに伝来した新種の農具で、関東地方の竪穴住居跡から発見される場合もあるので、その所持は支配者層がほとんどであるとはいえ、ある程度農民層の間にも行き渡った可能性がある。木工用の鉄器の普及と、鉄製耕耘用具の使用開始は、弥生期の湿地農法の限界を突き崩す決定的なモメントとなり、水田や畑が低湿地以外に広がっていく。
こうした農耕具のほかに田下駄・大足がある。田下駄は深田での刈り穂や肥料の運搬に使用され、大足は苗代への緑肥の敷き込みとかしろ踏み用具といわれており、田植えの存在を示す有力な証拠とされている。
収穫は、弥生初期の北九州では朝鮮南部や中国の長江下流の石庖丁に似た外湾刃月形の石庖丁が用いられた。弥生期を通じて収穫は稲穂をつむことが中心であった。石庖丁の使用は弥生後期まで続き、その後は鉄製の手鎌にその地位をゆずっていく。古墳期後半には、鎌身がゆるく湾曲し、先端の尖った大陸伝来の曲刃鎌が使われる。鎌は住居からの出土数が多く、耕耘用具よりも広く普及したらしい。また、曲刃鎌の登場から、稲の根刈りが行われるようになったとされている。
こうして、このころまでに、わが国に伝統的な鍬と鎌の農業の特質が、ほとんど出そろったのである。
豊穣への祈りと感謝
祭りは「心のふるさと」であるといわれ、全国各地に古くから受け継がれてきた祭りが数多い。わが国は四季の変化に恵まれ、「稲の文化」という独特の文化を形成してきた。稲作は現代まで2千数百年の長い歴史を経ており、日本人は稲作を通じて四季の変化を敏感に感じてきた。季節の変化は神の所作と考えられ、人々は神が起こす変化の中で神の意を伺い、従おうとした。神意を伺い、感謝する行為が祭りで、稲作の節目節目に行われてきた。
年の初めには豊作を祈る予祝行事がある。これには2系統あって、一つは「物作り」で稔りの印として餅玉や繭玉を飾る。福岡市では、正月3日に玉を奪い合い、玉を納めた者の村が豊作になるという「玉せせり」が行われる。もう一つは「庭田植え」で、稲作の作業過程を模擬的に演じて豊作を祈る。東京板橋区の「徳丸田遊び」、青森県八戸市の「えんぶり」などがこの系統にある。
春には桜の花見を行う。サクラは穀霊(サ)の宿る座(クラ)であり、桜の咲く丘で宴をもつことは豊作祈願の大切な行事でもあった。
苗代の水口に花や木の枝をさして供物を捧げた後、田植えの時期になると、目にも鮮やかな早乙女が中心の田植え祭りがある。大阪市住吉大社の「御田」、広島県千代田町の「花田植え」、三重県磯部町の「伊雑宮御田植神事」が知られている。田植え後には虫送りや雨乞い、風祭りなど呪術的な行事がある。岩手県滝沢村・盛岡市の「チャグチャグ馬ッコ」など家畜の無病息災を祈る祭りもある。
稲の収穫期にも祭りは多い。宮中の「新嘗祭」、九州の「おくんち」、さらに各地の秋祭りなど新穀を神に捧げ、春の豊穣祈願に対する報告と感謝を表わす。翌年の種子になる籾俵は田の神のように神聖視される。石川県能登地方では年の終わりに「餐の事」という田の神に対する感謝が行われるが、御神体となる二股大根が籾俵の上に鎮座ましまして土蔵で休息する。湯浴みや甘酒、供物でもてなしを受け、翌春の2月に再び田に送られる。
おそらく、稲作伝播以来、こうした祭りが絶ゆみなく続けられてきたのであろう。東南アジアなど稲作民族に共通する祭りも多く、稲作圏の人々が、稲とともに大地のサイクルに従って生きてきたことを物語っている。

大阪市住吉大社の「御田」