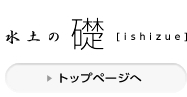コラム 農書の出版
近世における集約的農業の経験や知識を蓄積・伝達するに当たって、技術書としての農書が多く出版されたことは、各地で着実な活動を行っていた「老農」と呼ばれた人々の存在とともに重要である。多数の農書が読まれるのは、読み書き能力を備えた単婚家族による小農経営が広く展開するのに伴い、もはや農業技術が集団的な慣行や家伝だけでは維侍・伝承されなくなった状況を反映していた。
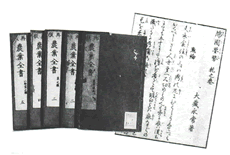
『農業全書』全5巻と大蔵永常の『綿圃要務』
全国各地で、多くは専門の著述家ではない著者により書かれた農書は、とりあげる作物が畑作物を中心に数多く、またそれぞれの作物に関する技術の記録も緻密である。品種や種子の選別、肥培管理、作付方式などの記述が精密化するのは、商品作物栽培を核とした畑作の集約化が進展したのと軌を一にしている。
たとえば、比較的初期の元禄10(1697)年に宮崎安貞が書いた『農業全書』でも、稲作中心ではありながら交換される作物への強い関心を示していたのであるが、幕末に近い広化元(1844)年の大蔵永常『広益国産考』にあっては、書名が示すとおり、各藩の殖産政策(国産化)の活発な動きのなかで特産物の育成を図る明確な目的をもって、全編、商品作物生産技術の記述に貫かれ、詳述されたもの30数種、その他を含め言及されたもの60品目にもおよぶ。
農書の記述は概して平易で具体的であり、合理主義的、なかには幕末期にあって科学(近代)的といえるような姿勢のものもあった。たとえば天保12(1841)年下野の篤農、田村仁左衛門吉茂による『農業自得』では、土性・肥料・気候を詳細に観察し、年々耕作帳に記帳することを通じて得られた経験をもとにしている。「古の農書にも…と記しおくなれども、よくよく試むると…し難し」というように、観察→考察→実験→確認という過程をふまえ、穀作はどれくらいの疎植がよいか、畑作ではどの作物とどの作物を輪作すべきかなどを記している。
こうした経験の蓄積により、肥料の効果を落とさず、いや地現象を起こさず、作物成育期間をぎりぎりのところまでつめた輪作体系の工夫がこらされ、限られた土地を最大限に利用した集約農業が実現・定着したのであった。