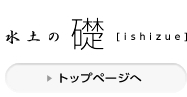農耕のはじまり、焼畑
わが国の山地には、古くから、おそらく縄文期以来、伝統的な農耕形態として焼畑が広く営まれていた。近世以前には面積にして20万町歩(約24万ha)を超え、昭和25(1950)年ごろでも5~6万haにおよんでいたとされている。「むさし」の「さし」をはじめ、東京付近にたくさんある「さす」「さし」のつく地名はいずれも、かつての焼畑の存在を示すといわれるほど広がっていたのであり、近世に確固となる小農自立の重要な基礎となっていた。
水田稲作農耕が同じ耕地で水稲を連作するのに対し、自然条件に適応した焼畑農耕の経営は、きわめて多様である。毎年、森林を伐採し、火入れを行って耕作のできる土地にしなければならない。3~4年作物をつくると耕作を放棄して休閑するのが普通で、1戸当たり全体で15~20ha程度、入会地などに占有している土地の中を、常に1.5ha内外の畑が転々と移動していくのである。
そこで栽培される作物は、アワ・ヒエ・ソバ・ダイズ・アズキをはじめ、イモ類・麦類・カブ類・トウモロコシ・ナタネ・エゴマなどときわめて多種におよぶ。これらを、伝統的な輪作体系の中で、年毎にソバ→ヒエ→アズキ→サトイモというように栽培し、また輪作の年次や耕地の性状によって、混植したり間作したりと複雑に組み合わせる。

新潟県栄村の秋山郷で伝統保存のため続けられている焼畑
食用作物ばかりでなく、コウゾやミツマタ・山桑・山茶など工芸・加工作物をつくる場合もある。生産性はかなり低く、安定性も低いため、狩猟・採集や木製品の製造、炭焼きといった他の生業と結びついていたらしい。
しかし、河谷の低地から山腹斜面を経て山項に至る垂直的、また峰から峰への水平的な山地の自然条件の変化を細かく認識し、それを生かして多様な経営が営まれ続けてきたことには、平地農村での単一の水田稲作とは異なるタイプの土地利用の合理性が生きている。戦後、生産性の低さのために急速に消滅するまで、九州・四国山地をはじめ全国の山村でかなり広く営まれていたのである。厳しい自然条件の中で生きる山村農民にとって、焼畑は、火入れという最も簡便な開墾法と、焼土による速効的な肥料・除草効果を活用した、山地へよく適合した形態であったと評価できよう。

焼畑の造成
夏に枝を伐採して枯らし、火入れをする。焼き跡にソバなどをまき、秋に収穫する。